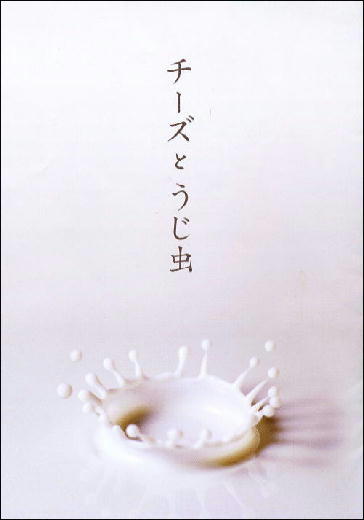お薦めシネマ
チーズとうじ虫
2006年7月
- 監督・編集:加藤治代
- 出演:加藤直美、小林ふく、加藤治代
- 配給:「チーズとうじ虫」配給委員会
2005年 日本映画 97分
- 22005年山形国際ドキュメンタリー映画祭小川紳介賞・批評家
連盟賞ダブル受賞 - 2005年フランス・ナント三大陸映画祭
ドキュメンタリー部門最高賞(金の気球賞)受賞 - 2006年イタリア・アルバ国際映画祭 招待
- 2006年スイス・ビジョンドリール映画祭 招待
闘病生活をしているお母さんを介護している女性が、家庭の日常をカメラで撮影したフィルムを撮るために、映画美学校に入りました。『阿賀に生きる』『花子』を監督した佐藤真のドキュメンタリーコースに入った彼女は、お母さんを撮影したフィルムを編集して卒業作品としました。それが、学校のスカラシップ作品に選出さて、予算がついてプロの手が加えられて、そして世に出ることになったという映画です。構成や繊細な撮影が、ドキュメンタリー作品として高い評価を得ています。
物語
加藤治代監督は、ガンと宣告されたお母さんを看病するために実家で過ごしている。そこには、治代さんのお母さんである直美さんと、直美さんの実母の、93歳になる小林ふくさんが住んでいた。
直美さんは畑仕事をしたり、ほうきに目印をつけて「ペンペン」と言いながら三味線の稽古をしたり、スケッチに出かけたり、油絵を描いたりと、充実した毎日を送っている。そして、楽しいお母さんである。ガンの宣告を受けたのに暗くない。
ある日、直美さんは、銀行から大金をおろしてきた。新車を買い、小さな耕運機を買った。畑仕事が楽になる。畑には、ナス、キュウリ、スイカ、トマトが実っている。
今晩のおかずは、ブリと大根の煮物。直美さんは娘の治代さんに料理の手順を教えながら作っていく。治代さんは、そんなお母さんとナベの中を、交互にカメラに撮っていく。
最初、カメラの前で恥ずかしがっていた直美さんも、カメラに向かってポーズをとるようになった。カメラの前で自然体になっていく。
治代さんのお兄さん一家に、4人目の子どもが生まれた。赤ちゃんを囲む上の子どもたち。
病室での点滴。髪の毛が抜ける。直実さんお手製の帽子をかぶる。死は一歩一歩やってきている。
髪がすっかり少なくなったが、退院した直美さんは、油絵の教室に顔を出す。先生の前に作品を並べて批評を受ける。
輸血。病院で過ごすお母さんの動きがだんだんなくなり、ベッドに横になっていることが多くなった。あいかわらずやさしい笑顔だが、ちょっぴり笑顔に力がない。しかし、死を覚悟して……という重さはない。
そして、次のシーン。白い布で顔を覆われた直美さんの遺体が映る。真っ白な布団に寝ている。この日は、来ないような気がしていた。この日は、来てほしくなかった。お母さんの死の場面は見たくなかった。しかし、直美さんは亡くなった。顔を覆った白い布が、そっと上げられる。とてもきれいな顔だ。眠っているように穏やかで、少しほほえんでいました。
やがて、孫たちが来る。コーちゃんから下の子たちは、おばあちゃんである直実さんの死がわからない。舜ちゃんは、おもちゃを持って直実さんの布団の足もとに寝ころぼうとする。大人たちからきつくしかられ、驚いて泣いてしまう。おねえちゃんのちーちゃんは違う。おばあちゃんの白い布団のそばにやってきたときから、心に何かを感じているようだ。線香を立てて祈った後も、おばあちゃんのそばから離れようとしない。じっとおばあちゃんを見ている。
直美さんが亡くなって、治代さんとふくさんの二人の生活がはじまった。直美さんの思い出を語りながら、夕食につく。ふくさんは、娘の死が悲しいが泣き言は言わない。治代監督が撮影したビデオをじっと見て、「直美より、わたしの方が美人だねぇ」などと言っている。次の日も見ている。

日常生活の中で、亡くなった直美さんを思い出しながら過ごしていく。「おかあさんは、○○だったね」と会話の中に出てくる。死者は、遠くにいるのではない、覚えている者の、心の中にいつもいるのだ。
治代さんは、2歳のときに父親を亡くしましたが、霊柩車が出て行く場面を鮮烈に覚えているそうです。そのときの思いから、お母さんがいなくなったらイヤだと、お母さんから離れられない子になりました。ですから、ガンの宣告を聞いたとき、母親の死を受け入れることができなかったそうです。
終わりのときを迎えて、直美さんが苦しんでいるとき、そして亡くなったときは、カメラを回すことができなかったそうです。治代さんは次のように言っています。
「母の死後、わたしは初めてある覚悟をもってカメラをまわしはじめました。なぜなら残された者は赤ちゃんの様に泣きながら、それでも前に這って行かなくてはいけません。そしてもしこの苦痛と重苦しい喪失感の中に、何か大切で優しい大きな意図を見つける事ができなければ、どうしてもわたしには母の死が納得できなかったのです。
わたしが撮る事ができなかったたくさんの悲しい出来事はある意味、わたしにとって撮る必要が無かったことかもしれません。なぜってわたしは今でも痛みを持ってその事をきちんと思い出す事ができるのですから。
それよりも、映像に記録していなければ記憶にさえ残らない様な、あの平凡で単調でそれでいて辛い母との時間が、ビデオを通して甘美で優しい普通の幸せに変わっていった事が、今は愛おしく感じられてならないのです。」
映画は、24の章で構成されており、それぞれにタイトルがついています。断片的な日常の映像にナレーターはなく、映像の中の会話が貴重な解説になります。ときどき写される空の映像が、とても印象的です。
だれでも体験する親の死。特別のことではありません。この映画は治代さんの個人的な体験の話ですが、だれでもが追体験できる普遍的な作品となりました。それは、直美さんの、ユーモアがあってやさしく前向きに生きている母親としての姿が影響しているようです。この映画には、涙はありません。自然な母と子の会話が続いていきます。こんなふうに死を生を受け止めていけたらいいなと思いました。治代さん、この映画を作ってくださって、ありがとう!